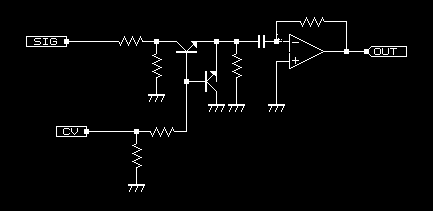通常のトランジスタ回路はB-E間にaudio信号を印加するわけですが、飽和抵抗を利用したVCR(電圧制御可変抵抗)回路の場合C-E間にaudio信号を印加するという操作を行います。
これは C-E間をVb(ベース電圧)の値で変化するVCRとして扱うためです。 可変抵抗として扱うためには制御信号で抵抗値が変化するのはもちろんのこと、印加電圧(audio信号)の大小で電流が変化し、電圧がプラスであれば電流もプラス、電圧がマイナスであれば電流もマイナスとなるという基本性質を有していなければなりません。
トランジスタが活性状態(線形領域)にある場合、Icは おおむねVbeに依存した定電流源となるため、 Vceの変動でIcは変化しないのだから抵抗体としては機能しないことになり、トランジスタを飽和領域で使用することによって、Ic(Ie)は Vceの変化に追従するようになります。
また飽和領域においては Vceがプラスの場合にIcの変化はVceに追従するのみならず、Vceがマイナスの場合もIcの変化は(-)Vceに追従します。 この(-)Vceというのはいわば逆(方向)トランジスタの飽和領域だからです。
| トランジスタのIcはVbeで変化するのでVbeが大きくなればIcが増加する。 IcはC-E間を流れる電流なので同じ印加電圧(Vce)であれば抵抗値が下がったことと同じ。 すなわちVbeの変化で抵抗値をコントロールできる。 但し、抵抗として機能するにはVceの変化そのものに対してIcが追従しなければいけないが非飽和状態ではそうならない。 飽和動作時はそれが可能だが当然Vbcはプラスの値の時であってVce=Vbe - VbcなのでVceは少なくともVbe以下でなくてはならないし実際はさらに小さい値しか印加できないということ。 |
問題は Vceの変化に対してIc(Ie)の変化はリニアな変化ではなく (-)EXPO特性になるということです。 また Vce固定で Vbeを変化させたときの変化は 通常の活性領域におけるVbeとIcの関係と同様、Ibが EXPOの変化になるため、 IcもEXPOの変化になります。 すなわち包絡線は EXPO特性であり波形自体は非対称波形(マイナス部分の振幅の方が 大きい)

* 包絡線(ENVELOPE) 無対策時

* 信号波形(信号レベルによる波形の違い) 無対策時
またVbeが増えるとIcが増えるので抵抗値が下がることになり場合によっては使いにくい場合(VCAとして使う等)があります。
* 裸の特性
* Vbeが増えれば抵抗が減る --- VCAmpでなくVCAtt.
* 波形(+),(-) 非対称、 エンヴェロープ expo特性
この為 VCAとして使用する場合の1案としては下図のようにエミッタフォロワのような形
にして、出力をエミッタ側から取り出します。

1: これにより Vbeがあがれば出力電圧も上がる。
2: エミッタの抵抗により負帰還がかかり、Ieに対してマイナス側でより負帰還がかかる。
3: audio信号=0V時の 制御電圧の急激な変化に対する OFFset電圧の軽減
4: さらにベース抵抗をつけるとIbの負帰還作用による非対称性の改善。
などが改善されるわけです。 ただこの場合、Vbが小さい領域では負帰還が十分働かないため非対称性はあまり改善されません。
またエンベロープはVbとIb, Ic,Ieの関係であるため、非線形なEXPOカーブであり、 VceとIb,Ic,Ieの関係も反映されているので EXPOカーブでかつ上下非対称なエンベロープ となります。 さらにエミッタ抵抗で負帰還がかかっているためIbが大きくなると エンヴェロープ波形は飽和するため、最終的には Ibが小さい領域で EXPO、中間の一部 でリニア、Ibが大きくなるとLOG --> 飽和という 1次HPF的特性となります。 当然マイナス側の輪郭のほうが先に飽和します。
この為上図のようにベースにも抵抗を挿入してさらに負帰還をかけることにより VbeとIb,Ic,Ieの関係をリニアに近く改善させるわけです。

上記回路の波形(かなり改善されています。)
さらに下記のようにtransistorの1個を逆に接続して補正を図った例もあります。

* ROLAND DR110のアクセント回路
飽和抵抗については トランジスタを可変抵抗(VCR)として使うを参照。